
起きられなくなった私
前回「ひきこもり放浪記 第1回」で書かせていただいたように、私はある商社の最終面接まで行っておきながら、自らそのチャンスをつぶす行動に出た。
頭で考えて選択したのでなく、身体がそう動いてしまったのである。
このように書くと、「意志の力」を信仰する人たちは、
「嘘をつくな。それはお前の怠け心のなせる業だ」
「死ぬ気になってやれば、何でもできる」
などと説教してくださる。
私自身、かつてはそういう意志全能教の信者であったために、自分の意志に反して動けなくなった自分を、どのように解釈してよいかわからなかった。
「何をやっているんだ、自分は」
猛反省して、動かない身体に鞭うって就職活動を続け、最終的にある旅行会社に内定を得た。人気ランキングの上位にあった会社で、ブラックな噂もなく、人々からは羨ましがられたのだが、私自身は無期懲役、いや終身刑の判決でも下された気分であった。
「これで人生が終わった」
しかし模範囚よろしく入社前の研修も無遅刻無欠勤で完璧にこなし、
「さあ、あとは入社式を待つだけ」
となったときに、私は朝、布団から起きられなくなった。
起きよう、と思えば思うほど、身体は冷凍された魚のように固まり、動かない。
「どうしてしまったんだ、自分は」
夕方になって、ようやく身体を起こすことができ、砂を噛むような思いで、人間が一日生きていたら最小限やらなくてはならないことを済ませ、また布団へ倒れこむ。
「人に会う」などという重労働は、逆立ちしてもできないから、自室にひきこもる。
入浴など、しなくても生存を続けられることは、すべて省略する。
布団に倒れていても、心地よい眠りに落ちるわけでもない。
ひたすら時間が過ぎていくのを、目を伏せ、横になったまま、得も言われぬ不快感を噛みしめながら耐えている毎日となった。
これで社会生活などできるわけがない。
布団から這うようにして出ていき、就職するはずだった企業へ内定を断りに行った。
「大学で必須の単位を落とし、卒業できないので」
と嘘をついた。
そのとき、それ以上詳しく訊かないで受理してくれた人事課長の顔が、今も忘れられない。後藤さん、ごめんなさい。こんな新聞、ぜったい読んでないだろうから、この場を借りて深くお詫びいたします。あの時はありがとうございました。…
存在を肯定してくれる言葉がない
必要な単位はすべて取っていたが、卒業しなかったので大学は留年となった。
「本校の制度上、あなたはあと2年まで、留年できます」
学務課の人に言われた時、私にはそれが余命宣告のように聞こえた。
留年と聞いて親は激怒したので、仕送りはもらえず、塾講師や家庭教師で稼ぐことになった。
なんのことはない、アルバイトと行き帰りをあわせたら、へたな会社員よりはるかに多忙な生活となった。それでも私の身体は、会社員になることを拒んでいたのである。
「身体は正直」
といった言葉を、それまで一度も深く噛みしめることのなかった私であったので、自分が何をやっているのかを、どのように他人に説明してよいかわからない。
また、強権的な母親に主体を剥奪されて育ってきた私は、
「目の前にいる他者が何と思おうとも、そのまま自分は、自分の在りようで、そこに存在しつづければいいのだ」
という良い意味のふてぶてしさをまったく持ち合わせていなかった。
となると、どうしても説明して、人にも自分の在りようを納得してもらわなければならない。
ところが、そうなると、説明する言葉がないのであった。
たとえ借り物でもいいから、言葉がほしかった。
家庭の平和より 人間の自由より まず勤労
時に、1986年である。
「ひきこもり」「内定ブルー」といった語は、まだ存在していない。
「フリーター」という語でさえ、誕生したのはその翌年である。
「五月病」「スチューデント・アパシー」という語はあったが、どうも自分と違うようである。
「モラトリアム人間」という語が広く知られていたが、自分のアイデンティティとして名乗れるだけの説得力の強さを感じなかった。
音楽とか、演劇とか、何かやりたいことがあって留年しているわけではない。
「なぜ留年しているの?」
と訊かれると、とりあえず水戸黄門の助さん角さんの動作をして
「院浪」
などとおごそかに宣(のたま)ってみるのだが、そのくせ大学院を受験する気などサラサラないのであった。
「冗談じゃない。これ以上、勉強も仕事もしたくない。
何もしないで生きていたい」
と思っているのである。
しかし、そんなことを実際に口に出して言ったら、これはえらいことになりそうな予感がした。
当時はまだ、それぞれの小学校の校庭に、二宮金次郎の銅像が立っていた時代である。
「勤労」ということが、何よりも尊ばれていた。
家庭の平和より、人間の自由より、まず勤労であった。
経済成長、所得倍増。
1960年代に日本中に充満したガスの残存物が、20年経ってもまだ社会に、濃厚に残っていた。
それどころか、時代は、バブルへ向かって狂ったように坂を駆け上がり始めていたのである。
(ひきこもり放浪記 第3回『バブル時代』へつづく)
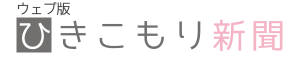

読ませますね。
こういうと、恐縮ですけど、まるで自分のことが書かれているように感じます。
わたし、受けた会社、「面接に来るように」といわれながら、すっぽかした経験あります。
そして就職浪人。
既卒で出て、ある人の導きで、幸運にも? とある会社に就職しましたが…。
30年いましたけど、人生の節目で、諸症状が出て苦しみました。
就職活動を自分でしておきながら、あのとき、なぜ、「著しい拒否感」といったものが出たのか、いまだに分かりません。
わたしは筆者と同じ年代ですけど、もう少し年齢は上ですね。
「シュチューデント・アパシー」…懐かしい言葉です。
ともひこさま コメントをどうもありがとうございます。
「まるで自分のことが書かれているように感じます。」
などとおっしゃっていただけて、筆者としては望外の喜びをおぼえます。
このように感じ、このように生きてきたのは自分だけか、と思いがちであったのですが、はばかりながら言葉にして発信させていただくと、けっこう同じように感じておられる方はいるものですね。
心強くも感じます。
今ではスチューデント・アパシーなどとも言わなくなりましたね。当たり前すぎて。
Hello everybody, here every person is sharing such know-how,
therefore it’s good to read this web site, and I used to visit this webpage everyday.