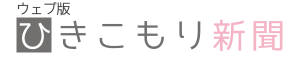「引きこもり」のエスノグラフィー
(文・写真 喜久井ヤシン)
前回「歳月の喪失 ~レナードの朝(上)~」のつづき
壊れてしまった時間
自らの心と体が動くようになっても、時は自分をおいてきぼりにして、現在の時間で生きていくことができない。眠りつづけていた歳月にも、世の中は激しく変わりつづけていて、同年代の人々は社会でそれぞれの立場を築いている。……L-ドーパによって「外」に出て、健常な生活を取り戻した人々も、なかった年月をあったことにはできない。その詳細な心境は想像するほかないものだけれど、からっぽの箱の上に重たい物を載せるような、支えていくには具合の悪い、バランスのとりがたい人生のかたちがあるものと思う。
また、一度は自由な生活をとりもどした人々も、運動障害などが起こるパーキンソン病を発病したことで、新たな病状に苦しむことになった。サックスはパーキンソン症候群患者の状態を、『空間や時間の中に迷いこんだ』、『壊れた時計や物差しの混沌』などと表現している。患者たちは、自分の体がなすすべのない塊となり、ふたたび虚無的な月日を過ごさねばならなかった。サックスの患者たちは、一度はよみがえったと思われた自分の時間が、また長い眠りへと引きづりこまれていく、二度目の喪失を経験することになった。
感情のなくなった年月
患者の一人についてサックスは、『生きた存在としてのいかなる感情も表さなくなり、車椅子に座った空虚な存在になってしまった』と記録している。
それでもサックスは治療を続け、患者の情動を引き出そうとするけれど、かんばしい成果は得られなかった。
『私は彼からなんらかの感情を引き出そうと躍起になったが、いつも失敗した。とうとう彼自身がこう言った。「私には感情はなにもないよ。内側が死んでしまったんだから」』
何十年もの歳月を、「外」に出ることなく、無動状態で過ごすためには、感情ほど邪魔になるものはない。……私は自分の経験をこめながらいうけれど……長い年月を最低限の生存活動だけで耐えるためには、どこかで情味が欠損していなければならないと思う。
感情の死を伝えているという点で、別の患者の言葉もある。
『「気分というものがなくなってね。周りのことはなに一つ気にならなくなったのよ。なにに対しても感情が動かなくなって、両親が死んだときだってそうだったわ。幸せや不幸せがどういうものか忘れていたのね。それが良かったか悪かったか?どっちでもなかったわ。だって、なにもなかったんですもの」』
「ない」ということもなくなるところに、長い年月を失わせるだけの、深刻な虚無がある。患者たちが人生の喪失に苦しみ傷むのは、感情を回復したあとのことで、失ったと感じられるのは、失っている渦中ではなく、自分を取り戻した時のことだ。
「レナードの朝」は残念ながら、奇跡の回復の物語として終わるのではない。安定した生活をとりもどした人もいるけれど、病からの目覚めに苦悩し、薬の副作用からくる激しい痛みのなかで亡くなった人もいる。表題になったレナードのケースでは、L-ドーパの効果が表れなくなったことで、元の無動状態へと戻り、再度治療を試みても、極度のチック症状に苦しむばかりとなって、人間的な活動はできなくなった。
サックスはこの後も患者たちの病を研究し、さまざまな手段を試したが、L-ドーパほど劇的な効果が表れることはなかった。「レナードの朝」は、感動のドラマのようにはいかない、現実的な、苦い終わり方となっている。
自分のための言葉を求めて
……私は古いノンフィクションを持ち出して、自分の過去を把握するための言葉を探しているのだと思う。人と出会うことを放棄して、人生を生きようとはしていなかったあの10年ほどの期間を、私はどうやって自分の一部としてとらえていいかわからない。自分と闘病のルポルタージュとを直接比べられないにしても、私は自分のための一つの比喩として、「レナードの朝」を読んでいた。眠りのなかのように、感情なく年月が過ぎさって、気づいたときには自分が年老いている、あの残酷な時間のことを、私は他人のこととしては読まなかった。「私」の空白的な期間に、痛みの感覚はあったとしても、寂しさや悲しさの感情は消えていた。ごく瞬間的な楽しさはあっても、深く味わえる喜びはなにもなく、私は私でいなかった。人のなかで生きられたはずの自分と、そうではありえなかった自分とのあいだには、致命的に欠損した歳月がある。その穴の大きさを測るための、尺度を見つけるようにして、私は言葉を探している。
参考文献
オリヴァー・サックス著 「レナードの朝 〈新版〉」 春日井晶子訳 早川書房 2015年