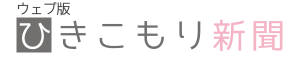前回「歳月の喪失 ~カスパー・ハウザー(上)~」のつづき
人生の途中から生き始めた人間
フォイエルバッハによるカスパー・ハウザーの記録は、冷たい研究対象の記述ではなく、時に熱い哀れみの感情が込められている。以下の箇所は、特に強い思いの込められた言葉のように思う。
『人生の初期のころ、動物的な眠りの中にいたカスパーは、その広範で美しい人生の部分を、(真に)生きることなく通り過ぎてしまったため、歳月は彼のものとならず、彼のかたわらをむなしく過ぎ去ってしまったのだ。彼は、そういったものが存在すること自体、知ることができなかったのである。〔中略〕彼が失った時間は、もうもどってはこない。やりなおすことなどできはしない。彼の精神が眠っていた時間に消え失せてしまった幼い頃というものは、決してとりもどせはしない。たとえ彼がどれほど長生きしたとしても、彼は、幼児期・少年期を欠いたままの人間なのである。(これは精神の)奇形であり、ふつうの人生とは異なった、人生のなかばから生き始めた人間なのである。』(※かっこ内も原書による。)
「私」はこのフォイエルバッハの文章を、完全に自分のためのものとして読んだ。冷たく暗い部屋を出て、大勢の人たちのいる明るい環境があるのだとしても、それで過去の歳月が帳消しになるわけではない。失われた歳月を取り戻せるわけはなくて、欠損したままで、また長い年月を生きることになる。
初めて世界の美しさを知って
カスパー・ハウザーには、生きなおしが必要となるような、新たな歳月のための苦しみがあった。
『彼は陽の光から目をそらしていた。窓を通して直接入ってくる光線を、実に注意深く避けていた。たまたま光が目に入ると、目をしょぼつかせ、額にしわを寄せ、苦しみの表情をあらわした。彼の目は血走っていて、あらゆる点で光に対する強い感受性を示していた。』
多くの人たちにとっては平凡な日の光でも、ハウザーにとっては目に慣れない、暴力的なまぶしさに苦痛があった。それにたぶん、単純な太陽光だけではなく、見慣れない人たち、見慣れない部屋、見慣れない景色の、平凡なはずの見えるもののいちいちが、ハウザーにとっては苦しみでありえた。
フォイエルバッハの記録によると、ハウザーは当初、牢獄で過ごしていた自身の境遇を、当たりまえのものとしてとらえていた。それ以外の生き方を知らなかったためだけれど、人間社会に解放された喜びはなく、むしろ、いつ元の暗闇に戻してくれるのかと期待してさえいた。それでも、常識的な生活や教育を与えられていく中で、ハウザーは自身の育った環境の異常さに気づいていく。
牢獄から出て、一年以上が経過したある夜のこと。彼ははじめて星空を直視し、その美しさに痛烈なショックを受ける。
『彼は叫んだ。「あれがこの世で見たものの中で一番綺麗だ。それにしても、これほどたくさんの美しいろうそくを、いったい誰があそこに置いたんだろう。誰が灯をつけ、誰が消すんだろう』
夜の星がどのようなものかを理解していないままで、彼は光を見て、その美しさを生まれて初めて知った。ハウザーは茫然自失となってから、しばらくして、自分を監禁した者への怒りと悲しみを初めて口にする。世の中に美しいものがあると知ったことで、彼の中で歳月が失われたのだった。
希望になるものに対して、輝かしいとか、明るいとかといった形容詞のつけられることがある。未来とか、明日にあたるものが本当にまばゆい光をともなっているとしたなら、それはその分、過去の歳月の暗い影を濃くすることになってしまう。星空のような世界の輝かしさと、それを知ることのなかった歳月の暗さ。それがコントラストになって、自分はいったい何を生きて過ごしてきたのかと、痛烈な喪失感になる。……言う必要はないかもしれないけれど、これらは「私」のために話している言葉だ。
カスパー・ハウザー 物語は終わっても
ハウザーがどのように変わっていったのか、どのような後半生を生きたのか、物語の続きは、彼の死によって途絶えてしまう。正体不明の者に殺されるという、ミステリアスな最後で、迷宮入りの事件になっている。生まれにおいても死においても、多くの謎を含んでいるところに、この伝奇が人を惹きつける要因があるのだと思う。
……私は、ハウザーの終わり方をずるい、と思う。怪奇的な事件や、人から注目を浴びるその渦中ではなくて、それから先の、なんてことのない何年、何十年の平凡な生活の中に、人間的な苦しみが多いのに。ハウザー自身の苦悩によって語られる言葉は、もうありえない。
「私」がこれから外に出て、社会の中に入っていくなら、親密な人との出会いや、未知の体験も、ないとはいえない。明日が本当に希望のある、光さすまばゆさを含むのだとしたら、「私」は世界の暗さによってではなく、明るさによってひるんでしまう。どれだけのものを知らないまま、どれだけのことをしてこなかったのか、そのからっぽさが、歳月を……というのか、年月を重ねてきたはずの自分自身を、担(にな)えなくさせてしまう。「私」には、過去の暗さも辛く、外のまぶしさも目に痛みすぎる。それなのに、また失われるかもしれない、歳月の上塗りになるものを生きていかないといけない。光の中のカスパー・ハウザーのつづきに、「私」は放り出されてしまっている。
歳月の喪失 ~カスパー・ハウザー(下)~ 終わり
参考文献
A・v・フォイエルバッハ著 中野善達・生和秀敏訳「野生児の記録3 カスパー・ハウザー 地下牢の17年」 福村出版 1977年