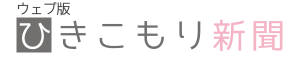(文・ぼそっと池井多 / Photo:Pixabay)
自己を大陸に缶詰めにする
前回「ひきこもり放浪記 第10回でお話ししたように、
スーダンの首都ハルツームへ向かう夜行列車の中で、
私はあらためて目の前に眠っている、
アフリカの人たちの顔をまじまじと眺めたのであった。
彼らは果たして、不幸か?
幼い頃から、母が私に言ってきたように、不幸か?
物心つかないころから、私がいだいてきた罪悪感のとおりに、不幸か?
私にとってアフリカ大陸とは、
その答えを思索するためにひきこもる場所であった
といって過言ではない。
「ひきこもり新聞」紙版2017年9月号4面に書かせていただいたように、
のちに私は30代のころ、
洞窟のような部屋の中に外界と隔絶してひきこもった。
この「ひきこもり放浪記」に綴(つづ)らせていただいているのが「そとこもり」ならば、30代のそれは「うちこもり」であった。
その「うちこもり」も、後から考えれば、
この「そとこもり」と同じく
或ることを徹底的に思索するために、
私が知らず知らずのうちに己れに設けていた歳月であった。
私がその必要性を感知していなくても、
魂がそれを求めていて、
結果として私が魂の要望をかなえるために、ひきこもるのである。
そのように書くと、なにやらオカルトじみて聞こえるが、
平たくいうならば、
ちょうど、原稿を書き上げなくてはならない流行作家が、
ホテルの部屋に自らを缶詰めにするようなものである。
平常の生活を送っていたら、外界との情報のやりとりに忙しく、
内界で情報を発酵させることができない。
そこで、しばらく外界と隔絶することが必要だと魂が判断し、
人はひきこもるのではないだろうか。
しかし、人は問うであろう。
「いったいアフリカ大陸という、開放的な空間のどこが
ひきこもり場所たりえるものか」と。
日本への連絡はどうしていたか
どこまでも果てしなくひろがる広大な大陸が、
私にとって20代のひきこもり場所となった理由の一つは、
その隔絶性にあった。
私が生まれ育ち、日常世界となっていた、
日本社会からの隔絶である。
当時はまだインターネットがなかったという事実が大きい。
一部にはすでにあったらしいが、とうてい一般には普及していなかった。
日本でWindows3.1が発売される2年前のことである。
今ならば、たとえサハラ砂漠のど真ん中であっても、
GPSで自分の位置を割り出し、
日本とメールやチャットのやりとりができるだろう。
ネットカフェがどこの都市にも存在し、
ちょっとした宿にはWi-Fiがついているだろう。
しかし、これらは
私がアフリカ大陸をうろついていたころには考えられないことである。
本稿の舞台となっている1989年に
たとえば私が滞在していたワディハルファという町から
何か急に日本へ連絡したいことが生じたとする。
手紙を書いて航空便(エアメール)で送る手もあるが、
郵便局に投函した手紙は、まず首都の空港まで輸送されなくてはならない。
ところが首都へ向かう列車が出なくて、
私自身が村に足止めをくらっていたわけだから、
私が発つまでは、手紙も村から一歩も外へ出ることはないのである。
けっきょく手紙は、私と同じ列車で首都に着くことになる。
そこでの郵便業務も日本のように早くはない。
スーダンから航空便が日本に着くには平均1か月半を要していた。
途中で消えてしまう郵便物も多かった。
「そんなに待っていられない。電話にしよう」
と考えたとする。
辺境の村ワディハルファまで敷かれていた電話線は、
とちゅう砂漠のどこかで切れているらしく、電話は通じなかった。
そこでやはり何週間もかけて、
電話をかけるために首都まで出ていくことになる。
首都に着くやいなや、目指すのはその国の中央郵便局である。
そこには、たいてい1台から3台くらいの電話ボックスがあり、
電話交換手がかたわらに座っている。
交換手に通話希望先、たとえば日本の実家の電話番号を告げると、
しばらくそこで待つように言われる。
そのあいだ交換手は、はるか遠い国へ電話回線をつなげようと、
何やらしきりと奮闘している。
そして、とつぜん「2番へ!」などと言われる。
日本へ電話がつながったのだ。
こちらは指示された電話機へ飛んでいく。
この瞬間から、秒単位で高額な国際電話料金が加算されていく。
海外と通話したければ無料の手段がいくらでもあるという現在では、
ほとんど考えられないほど、当時の国際電話料金は高かった。
スーダンのような最貧国であれば、
へたをすれば現地の人が一年という時間をかけて稼ぎ出す金額が、
ほんの数分で消えていくのである。
そこまでコストをかけて、せっかく電話がつながっても、
時差などの関係で、日本側が出るとはかぎらない。
この時代の「日本との連絡」は、このようなものであった。
頭の情報処理が追いつかないからひきこもる
大正時代までは、国際的な連絡は船便と電報に頼っていたわけだから、
バブル経済の時代は、
「地球の裏側と話ができる」
ということで、
当時の私は浅はかに文明の進歩を感じていたくらいである。
けれども、一般人がアフリカのような所へ行くからには、
事実上、日本とは連絡が途絶すると考えなくてはならなかった。
だからこそ、私はアフリカへ行ったのだと思う。
もし、健全な家庭環境に育ち、
両親との関係が良好なものであったならば、
私はわざわざ連絡の取れない場所へ出かけなかったのではないか。
いや、そもそもアフリカへ「死にに行く」などということは
考えなかっただろう。
ふつうに社会生活を営んでいると、
さまざまな人に会わざるをえず、
そのたびにさまざまな情報が入ってくる。
ところが、私のような慢性うつ病型の人間は、
頭の情報処理能力が小さいのか、
それとも情報処理の精度が高すぎるのか、
入ってきた情報の咀嚼(そしゃく)と消化が、流入に追いつかないのである。
コンピュータに例えれば、
CPU(中央演算装置)の型が古いということなのだろう。
飛びかう情報量が多い現代にふさわしい型のCPUではない、ということだ。
型が古いなりに、いつもCPU稼働率100%でフル回転しているのだが、
演算のスピードが追いつかない。
*
もっとアナログな例を挙げよう。
たとえば、自分の身体よりも大きな動物を餌として呑みこんでしまうヘビがいる。
獲物が体内で完全に消化されるまで長い間、
ヘビは喉や腹をふくらませたまま、物陰でじっとしているらしい。
これは私と情報のかたまりに、関係を置き換えることができる。
社会へ出ていくと、
消化できないほどの情報のかたまりを呑みこんでしまうので、
しばらくひきこもり部屋という物陰で
私はじっとしていなければならないのである。
このように情報処理のスピードが追いつかないときに、
できることといえば、
情報の取り入れ口を小さくすることである。
ちょうど、鎖国時代の日本が、
海岸線のどこからでも世界の情報が入ってきてしまうのを避けるために、
入り口を長崎と平戸だけに限ったようなものである。
その結果が、「ひきこもり」と呼ばれる生活形態になる。
アフリカを放浪している間も、
私にとっての日常世界である日本社会からの情報の流入は、
その隔絶性によって
日本国内にある暗くせまい部屋の中にひきこもっているのと同じほどに制限された。
そのぶん私の頭のCPUは、他のタスクに稼働を割り当てていたのだと思う。
すなわち、
「アフリカの人たちは不幸か」
を見極めるというタスクに。
・・・「ひきこもり放浪記 第12回」へつづく
——————————
紙面版ご購入はこちらをクリック
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ