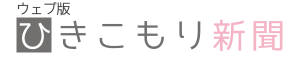「引きこもり」のエスノグラフィー
(文・写真 喜久井ヤシン)
学校へ行かなかった『私』
……二十歳くらいの頃、地下鉄の、新宿線に乗っている時だった。車内は雑談している会社員とか、制服姿の中高生たちが座っている、べつにどうということもない風景で、「私」はドア脇の柱にもたれて、カバンの中から哲学書を取り出した。
外で読書をしても頭に入ってこないのだけれど、あたりの景色が目に入ると、神経がピリピリとして耐え難くなってくるので、気をそらすために、車内では本を開くのが習慣だった。
けれど、その時にはふと、「私」は強い虚しさに襲われた。今自分のまわりにいるのは、就学や就労をしている、いってみれば「ふつう」の人たちばかりだ。テスト勉強や面接試験を経ているわけで、ということは、学力的な知力の面では、教育を受けていない自分が、この車内で一番劣っているのだろうと思った。
車内では、スマホのゲームをしている人とか、無駄話をしている人とか、それぞれが適当な過ごしかたをしているけれど、「私」は神経過敏な頭で読書しようとしている。
それでも、仮に車両内の全員で学力テストを受けたら、どれだけ今脳みそを使っているかなんて関係がない。一番点数の低い、評価されることのない、出来の悪い頭をしているのが自分だ、と思った。
二十代で小学生の勉強をする
「私」は七歳から公教育の場には行かず、教科書で教わる勉強の機会はほとんどなかった。通知表の成績覧は、数字ではなく斜線しか見たことがなかったし、「偏差値」というのは、自分のものとして話題になったことは一度もない。
精神的な混乱などから、学習塾やフリースクールにもほとんど行かなかったので、「私」のわずかな学業は、ぞんざいな自習があるだけだった。
二十歳を過ぎてから、人生で初めてお金を得る労働(アルバイト)を して、「私」の無知があらわになったことはきつかった。学力というよりも、社会生活での基本情報みたいなものだけれど…、「私」は「佐藤」や「鈴木」という字を書けなかったし、税金の出し方……小数点を使う、定価×1.08というもの……が可能だということを初めて知った。
業務をしていて、ちょっとしたメモ書きとか、ちょっとした計算とかに、「私」のできなさが表れていて、それは労働先をすぐに辞めた原因の一つになったと思う。
これまでの人生で何度か、「私」は子供向けの学習テキストをそろえて、基礎を学びなおそうとした時期がある。
「数学」では難しすぎるので、9歳児向けの「算数」からやりなおして、文字の大きい、低学年向けの市販教科書をやった。
…図書館でその教科書を開こ うとしたこともあるけれど、細かな字でノートをとっている中高生がいて、自分との差に恥ずかしくなって帰ってしまった。
自習は数週間で途絶えて、テキスト一冊を完遂することもできずに、みすぼらしいやりかけのノートが何冊か残されただけだった。
『学校の勉強なんて役に立たない』…か?
…基礎的な学力はともかくとして、人よりも多く本は読んできたし、映画を観たり、美術館へ行ったりして、個人的な教養は手に入れてきた。
…たとえ公教育場に通っていたとしても、天才になれたわけではないし、偉大な知性が得られたわけではない、ということもわかる。「学校の勉強なんて、社会に出れば役に立たない」とか、「これからの時代、知識だけあってもしかたがない」とか…そんな主張に同意できる部分もあるのだけれど……、私はやっぱり、基礎的な知識すらないのは、社会の前線に立つならば論外だと思えてしまう。
私は「私」の人生に、勉強があってほしかった。それは学歴がないとか、資格を一つも持っていないとか、社会的なデメリットだというだけではない。自分にも叡智がありえたという、空想をなくせないせいだ。公教育があったなら、一生を震わせるような知的な出会いや、未知の学識にふれて、骨ごと痺れるような興奮の電流に打たれるような、そんな人生の可能性は高かったはずだ。
一時期の「私」のお気に入りの空間は、紀伊國屋書店本店五階の奥、哲学書の並ぶコーナーだった。文章が読めない時期も長かったけれど、この世界の真理をあばくような、スキャンダラスなゴシップが書物の中に秘められているような気がして、本を買うつもりもないのにたちよることがあった。広いフロアを埋め尽くす書棚に囲まれながら、「私」には貪欲な知的欲求と同時に、それが叶えられない猛烈な喪失感があった。「私」は本当は、乾いた書物の山に対する、知覚の火事になってみたかった。古今東西から集められた人類の遺産を、読むことで焼き尽くして、自分の眼で貪(むさぼ)ってみたかった。
……「私」は、社会に対する静かな憎悪と、自分の知性への自負を込めながら思っている。公教育制度があれほど残酷な疎外をしなかったなら、「私」はこの人生で、はるかに大きな叡智とめぐりえていたはずだ、と。
走りつづけたウサギ 眠っていた亀
「これから勉強したらいい」とか、「まだ若いんだから頑張って」…とか、そういう励ましの言葉が「私」に反響してくることはある。定年退職してから勉強を始める人や、高齢になってから活躍しだす人も、今の日本社会ではよくあることだ。
「ウサギと亀」の民話でたとえるなら、大人になって勉強をやめた「眠ったウサギ」を、自分のペースで学び続けていた亀が追いこしていく…みたいな、学業面での逆転劇だって、ありえることはわかる。
ゆっくりとであっても、歩みつづけていれば、いつかはウサギも敵わない、遠いところにたどり着けるというような。
…ただ、「ウサギと亀」の立場でいうなら、「私」は眠っていた亀になるだろう、と思う。眠ったウサギどころか、歩みつづけていた亀にも追いつけない。
目を覚まして山を見上げたときには、走りづつけたたくさんの優秀なウサギたちも、勤勉な亀たちも、はるかな遠いところにいて、「私」は、致命的な距離にたじろいでしまう。
「他と比べないようにしよう」とか、「地道に頑張っていけばいいんだ」なんて言葉もむなしくて、もう一度歩きだそうという気力は、くじけてしまう。
「私」は現実を直視しないために逃げだそうとして、そしてまた、距離よりも遠いものが、失われていくことを感じている。
——————————
紙面版ご購入はこちらをクリック
ひきこもり新聞をサポートして下さる方を募集しております。詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ