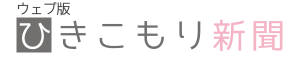「引きこもり」のエスノグラフィー
(文・喜久井ヤシン)
『親孝行』 なんてできない
母の日でなくても、親孝行や母親を賛美するメッセージは世の中にいくらでもあって、音楽や本でも、「おかあさん ありがとう」みたいな言葉がたくさんある。
歴史的には、中国で出来上がった「二十四考」という書物があって、親孝行がどれだけ素晴らしいことがが、延々と書かれている。
そこでは、田んぼがかってに耕されるとか、黄金の壺が出てくるとか、…私からするとコメディなのだけれど、親を大事にすると、なんでもかんでも奇跡がおきて、しかも聖人として語りつがれるらしい。
そういう内容の書物が、日本でも何百年か読みつがれてきて、たぶん親孝行のテーマ自体は、今の道徳の教科にまでつづいている。
私と母親との関係は悪くて、今でも顔を合わせることや、世間話をするだけでも難しい。
きっかけになったのは、私の教育マイノリティ(不登校)の発覚だった。
ある朝は、母が私の背負っているランドセルをつかんで、小さな体をひきずり、公教育の場所まで引っぱっていこうとした。私の心には無理解で、叩かれたこともあるし、なじられたこともある。母が絶望的な目をしながら、般若の形相でにらんだ時のことを、幼い「私」は脳みその深いところで記憶してしまっている。
にもかかわらず、公教育のこと以外では、私に毎日のように好きな食べ物を出したり、簡単にオモチャを買ったりしていた。
「お前はお前であってはならない」、というくらいの否定と、野放図で底なしの溺愛とが同時にあるみたいで、そのバランスの悪さから、私の精神状態はぐちゃぐちゃにされていたように思う。それは母との関係に限らず、私が生きていくうえでの、個人的な人間関係の築き方に、ひどくダメージを負うことだった。
母親への後悔の手紙
私は母を憎んだし、狂ってしまうくらいの苦しさがあった。そこには怒り以上の怒りがあったし、悲しみ以上の悲しみがあった。
生命のかかわる単位でいうなら、自殺を考えたことが八割、他殺を考えたことが二割ある。…それは、母のことを慕っていなかったということではなくて、むしろ愛して、どこまでも尽くそうとして、その情愛の深さがあった分、ありえないほど深くまで憎めたのだと思う。むしろ、唯一「母親」というものを憎む権利をもつのが、当の子供ではないかと思う。
子供にとって、母親を愛することくらい簡単なものはない。
私は思う。………私はあなたを、「良い母親」にしてあげることはできなかった。
あなたは一人上京して、長いあいだ働きつづけて、女性としては異例の昇進をした。
努力して生きぬいてきたあなたを、私という付属品によって、「完璧な女性」にして完成させることはできなかった。
私は命がけであなたの望みどおりの人間になろうとしたけれど、思い通りの、「良い子供」になってあげることはできなかった。
私はどこまでも自分を犠牲にして、あなたの一挙手一投足の言いなりになっていたつもりだった。
けれど、あなたが世間から「良い親子」と見なされるためには、私は使い物にならないクズだった。理想像を完成させるための機械になれなかったことで、私は長い年月、自分を責めつづけた。そこからくる人間失格みたいな劣等感は、この人生でこれからも、ずっと残り続けると思う。
…あなたからの評価がすべてだった自分のあり方を、私は二十歳前になるまで疑いもしなかった。
親を親と思ってはならない
どういうかたちであれ、親と対話が必要になったときや、断ち切れないこの関係について考えるときに、私には言葉の工夫が必要だった。
重要な線引きの一つとしてあったのは、親を「親」と思ってはならない、ということだった。
子供が親を責めることに対して、どれだけの重圧があるかわかるだろうか…。親を悪く言うような人間は、精神的に未発達で、人格的に問題があるみたいな見方や、子供の側の誤解や過剰反応に変えられてしまうような抑圧がある。
アダルト・チルドレン関連の本でよく書かれていることだけれど、暴力や性被害を受けた子供でさえ、相手が「親」というだけで、憎むことも嫌うこともできなくなる。
力をふりしぼって正当な抗議をしようとしても、本来正当なはずの訴える側が、圧倒的な悪になって、自分を加害者みたいにして自己叱責してしまう。
不均衡な力関係のなかで、「親子の対話」なんてものがあったら、子供の側が即敗北する。母親が「母親」であるというだけで、声をあげることなんてできなくなってしまう。
私と親は別の人間
私はある時期から、対話が必要なときには、「親」ではなく「養育者」だと考えるようにした。
「母親」を「女性養育者」、「父親」なら「男性養育者」と。「親と子」ではなく、「母親と息子」でもない。
そこを否定して、人間一人と人間一人の関係にまで持ち込まないと、一対一の理性的な話をすることなんて、私には不可能だった。言葉一つの違いだけれど、わずかな意識の変更から、私はこの関係性をめぐる闘争をしようとした。
対話のために問題になるのは、社会的規範の「子」や「親」であることでもないし、「家族」だからということではない。
「お腹を痛めて産んだ」ことは、話すべき本題とは分離させる必要がある。
「親」ではなく「養育者」であれば、伝統や歴史とセットにされるような、家族主義とも線引きができる。
親と子を描くテレビ番組みたいな美談もまったくいらないし、ハッピーエンドの起承転結におさまる「絆」の話でもない。
目の前に立つのは「おかあさん」なんて呼ばれる相手ではなくて、「養育者」に限定される。話さねばならないことを話すときには、(…あなたがずっとそうみなしてきたように、)「あなたのための私」の話をするのではない。
「良い母親」も「良い子供」もいない。「母親の子供」も「子供の母親」もいない。
一人の人間と、別の一人の人間が話をするために、「私」個人と、「あなた」個人との立場が必要だった。
…ただ、もちろん数十年来私を育ててきた事実があって、良くも悪くもしがらみになった思い出があるので、根づいてしまっている関係性を、すべて断ち切ることは不可能だ。
私が知っている養育者は、養育者の人生の数分の一にすぎなくても、養育者は私の100%を知っている。個人的な生き方や、別の場所での成育があったなら、そのパーセンテージは減ってくるものだけれど、長く家にいた私には、100%が養育者の手中にあると思える。
(「引きこもり」のエスノグラフィー「親孝行の技術~親を親と思ってはならない~(下)」へつづく)
——————————
紙面版ご購入はこちらをクリック
ひきこもり新聞をサポートして下さる方を募集しております。詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ