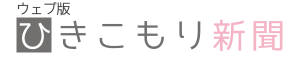自分のお金を手に入れた安堵
通りすがりの茶髪の高校生たちが、笑って「バイト」について話しているのが信じられなかった…。
「引きこもり」の「私」にとって、労働は精神を賭して挑戦しなければならない危険な行為で、気軽な世間話として「バイト」なんて言い方をすること自体がありえなかった。
それでも二十一歳の時、精神的には不安定だったけれど、数日の短期間労働をして、「私」は自分で稼いだお金を手に入れた。金額としてはわずかなものだけれど、賃金を得たことは、自分が社会人として不能ではないのだという証明みたいで、「私」は心から安堵した。「好きなものが買える」とか、「貯金ができた」とかいう種類の嬉しさはまったくなくて、社会性と関わる大きな安堵だった。
プロレタリア文学の一つで、こういう短歌がある………、
『我が命のかけらのように我が手より、いたましくも銭のはなれゆくかな』
………指先から金の離れていくことに、命が千切れていくような痛みを感じる…と詠んでいて、貧困の辛苦を感じさせる一句だと思う。
「私」が賃金の獲得で感じられたのは、この句の反対の出来事にあたる感覚だった。お金を手に入れたことによって、「私」は社会的な命がある……というか、肉体的な部位でいうなら、自分自身に腕がある、とか、脚がある、といえるくらいの医術的な安堵を感じた。
自分のお金があって、それで自分の好きなものを選んで買えるというのは、一般的には平凡だけれど、「私」が体験してこなかった、大いなる効力感だった。
ドストエフスキーのお金論
重々しい本だけれど、ドストエフスキーの「死の家の記録」(工藤精一郎訳 新潮文庫)では、心理的な側面から、お金がどれだけ重要な意味を持つのかを書いているくだりがある。
本は十九世紀のロシアで出版されたもので、作家自身の過酷な収容所体験を元にした、獄中手記の体裁をとって成り立っている。
ドストエフスキーはそこで、『絶対的に断言できるが、獄内ですこしでも金をもっている囚人は、ぜんぜんもっていない囚人の十分の一も苦しまずにすんだ。』……と書く。
生活必需品は全部支給されているので、お金があってもなくても、収容所内でのくらしぶりが根本的に異なることはない。それでも、金銭の有無が生命にかかわるくらいの重大事だということを、作家はくり返し強調する。
『もう一度言うが、もし囚人たちが自分の金をかせぐいっさいの可能性を奪われたとしたら、彼らはあるいは発狂するか、あるいは蠅のように死んでしまうか(何もかも保証されているといっても、それは別である)。あるいは、ついには、いまだかつてないような凶悪犯になってしまうかもしれない。』
けれど、金が計画的に使われるかというと、そうはならない…。
『囚人がほとんど血のにじむような汗をしぼってわずかばかりの金を得て、あるいはそれを得るために途方もないことを考え出し、よく盗みやだましというてまでつかっても、そのくせはいった金はまるで無分別に、子供としか思われないほど無意味に浪費してしまう』…。
苦難を乗り越えて手に入れたわずかな金を、囚人たちはあっけなく使い果たしてしまう。
そもそも収容所内なので、特に良い物が買えるわけでもなくて、この消費のあり方は物欲のせいとはいえない。にもかかわらず、なぜ激しい浪費をするのか……。
作家は、『囚人にとって金よりもひとつ上のものとは、いったい何だろう?』と自問自答して、直後に解答する。
それは、『自由、あるいは自由に対するせめてもの憧れである。』…と。
『「囚人」という言葉の意味は自由意志のない人間ということである。ところが、金をつかうことによって、彼はもう自分の意志で行動しているのである。』
お金を使う行為によって、囚人たちは、『自分には他人が思うよりも何倍も自由意志と権力があるのだということを仲間に見せ、せめて一時でも自分もそう思いこむことを、おそろしく好んだ――』。
物欲を満たすためとか、手に入れた物をどう使うかとかではなくて、買うこと自体に意志や選択が働いていて、それが制限された環境下での重大な自由になる。……そこにお金の意味がある。
お金を使えるという自由さ
「引きこもり」をめぐる話のなかで、数少ないけれど、「無理して働かなくていい」とか、「そのままでもいい」、といったメッセージを出してくれる例はある。
私としても、強制的に労働へ押し出すなんてあってはならず、当人にとって快適にすごせるのが一番良いと思う。
社会的に見ても、年金暮らしの高齢者とか、不動産収入か何かでお金が入る人とかもいるし、すべての人が働いているわけではない。
収入が問題にはなってくるけれど、社会的なセーフティネットや、身近な人からの金銭的援助で手立てはある。
…ただ、どうしようもないくらいあたりまえのことだけれど、お金には「稼ぐ」ことだけではなく、「使う」面がある。労働や収入がなくても、生きている以上、消費することだけは残る。
「私」が自分のお金を得て深く安堵した要因は……まったく大げさな言葉ではないのだけれども……消費に対する自由の獲得だったと思う。
養育者の提供する生活費を使うのは、ずっと罪悪感があって、「私」は物欲を抑圧していた。それが自分のお金を得たことによってやわらいで、「私」はひとときだけ、世の中の消費者としては平凡な、社会人の自由を味わったのだと思う。
以上
(文・喜久井ヤシン)
紙面版ご購入はこちらをクリック
サポート会員募集中!詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ