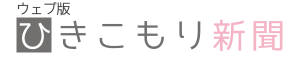道を歩くだけで痛むことがある
たとえば・・・たとえば道を歩いていた人が、まるで針でも刺さったみたいに、いきなり痛みを訴えたとする。誰もが平然と歩いている町なかで、その人一人だ けが痛いと言う。
その理由を聞いてみれば、「道を歩いたから」、「風が吹いたから」などと言ったとする。変わったところのない歩道で、病気のような体のなかの痛みではなく、外からの刺激が痛いと言われても、他の人にとってはわけがわからない。
けれどその人の皮膚に傷口があって、外気にふれることによって痛みが出ていた、とわかれば説明にはなるし、ああ風があたって痛かったのか、と納得もできる。そういうことならその傷口をかばう方法はないか、と次の動きも始められる。
体の傷なら人の目に見えて理解されることはできる。
それでも安直な言い回しで「心の傷」とでもいうような、抽象的で目に見えない傷口の場合ならどうだろう。
「道を歩いたから」、「人とすれ違ったから」痛むのだ と伝えても、説得力をもつのはむずかしい。場合によっては、他人の目では見えないために、仮病ではないかと疑われてしまう。
医者は傷ついた人の方を診る
たとえば・・・たとえば人から思い切り頬を殴られた人がいたとする。
その人の頬は腫れ上がり、内出血によって青あざができてしまう。その傷ついた人を見て、「あなたの頬は弱い」とか、「あなたの頬は病気だ」なんて言われたとしたら、そんな見立てはおかしい。
勤勉そうな医者が診断をして、「あなたの頬には何か異常があるのではないか?」なんて分析をされはしない。痛みの原因は殴った側が悪いのであって、殴られた側の、それも頬に特定の問題があったということではない。
けれど残念ながら 、精神医学や過干渉な支援家はそのように扱うことがある。
青あざができて痛みを感じるのは体の動きとしては必然で、「異常」どころかその健康なしるしでもある。それと同じように、・・・「引きこもり」の弁明になるけれど・・・人との関係に傷ついて外に出ることを拒む状況には、病態ではなく、むしろ心の動きとして必然的な健常もある。
外に出ることが恐ろしかった
十代後半から二十代にかけて、私は家の外に出ることを恐れた時期が長くあった。
教育上のマイノリティにされたために社会との関係は極めて悪く、学校の教師やサポートセンターの職員との不和もあった。傷つけられることが多く、「外」のすべてが 私にとって立ち入るべきでない危険地帯だった。
外出そのものができない「閉じこもり」ではなかったけれど、ドアを開けるまでに半日かかるくらいの覚悟を要したし、自分の外見がおかしくないかと、くり返し鏡を見ては髪や服装を確かめていた。
めったに起こらない危険と感じる出来事を「事件」と言っていいなら、「他人と目が合うこと」や「他人と会話すること」は当時の私には事件だった。
自分と外の世界とには長い確執があって、外出時には静電気を浴びつづけているみたいな神経の過敏さに見舞われた。
車がこなかったとしても、誰であれ信号が赤の道路を渡る時には「道を歩く」意識を強めるだろうと思う。
けれど私には平凡な歩道を行くすべての瞬間が、赤信号の横断中みたいな小さな過誤を 犯している気分だった。
歩いている最中にずっと小さな悪や不適切さが自分に含まれていて、人からどのように見られるか、またはなにか自分に関わる恥辱的なことが発覚するのではないかとおそれていた。
道を歩く意味は人によって違う
「道を歩く」なんてシンプルなことでも、それが経験として完璧に共有されるわけではない。よく晴れたあたたかな四月の日に、太陽の気持ちよさを味わう人もいれば、重度の花粉症で春を憎しむ人もいる。
また皮膚がんの人にしてみれば、紫外線を含んだ太陽光は害悪としておそるべき対象になりえる。
同じ場所であっても感じられるものは人によって違うし、「道を歩く」経験の重大さも人によって違ってくる。
何のへんてつもない交差点を恐怖する人がいたとしたら奇妙だけれど、その人が昔ひどい交通事故にあった現場なのだとしたら、恐怖することはむしろ必然だと思う。
喩えをひろげるなら、事件現場であり被災地と言える場所が、「外」の全域だったとしたらどうだろう。どこを歩いても、大怪我をした場所や被害を受けた地元のように、平然とは入り込めない精神的な痛みを感じるのだとしたら。
いつだって風は吹いている
コンクリートの黒粒を敷きつめて舗装された平坦な歩行路。柱組みで作られた白の塗装が剥げつつあるガードレール。選挙広告の掲示された電柱とそこに入り乱れて巻きついている電線。それぞれの日常を抱えて交錯し通りすぎる大勢の人々。
――それら平凡な歩道の風景が特別なところなく流れているのだとしても、私にとっては数十年の悲嘆が染み付いた暗い沈鬱の象徴にもなるし、人が自分に敵意を向けてくる苛烈な前線にもなる。「引きこもり」的な心象の強まっている私が玄関のドアを開ける時には、多くの苦渋を覚悟して、緊張や不安を小さな体に押し込んで足を踏み出さねばならない。道を歩くことは難しいし、いつだって風は吹いている。
以上
「エスノグラフィー」は文化人類学から生まれた言葉で、調査対象となる集団と共に生活するなど、現場へのフィールドワークによって記録がなされる研 究方法のこと。
本稿は「引きこもり」当事者による経験談だが、「引きこもり」の渦中にあっては書くことのできなかった精神面での分析も綴られている。自分自身を研究対象とするような距離感を表すために、エスノグラフィーというタイトルがつけられている。
文・喜久井ヤシン・・・小学校二年から教育マイノリティ(不登校)となる。中学の三年間は交友関係をもたなかった引きこもり経験者。
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ
ご購入はこちらをクリック