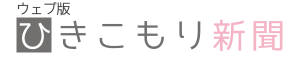「エスノグラフィー」は文化人類学から生まれた言葉で、調査対象となる集団と共に生活するなど、現場へのフィールドワークによって記録がなされる研 究方法のこと。
本稿は「引きこもり」当事者による経験談だが、「引きこもり」の渦中にあっては書くことのできなかった精神面での分析も綴られている。自分自身を研究対象とするような距離感を表すために、エスノグラフィーというタイトルがつけられている。
文・喜久井ヤシン・・・小学校二年から教育マイノリティ(不登校)となる。中学の三年間は交友関係をもたなかった引きこもり経験者。
火傷した手で火について書く(「私」が書き始めることについて)
私の「引きこもり」経験は……なんて平然と語りだしてしまっても本当に良いのだろうか。自分自身の「引きこもり」の記憶をよみがえらせて、人や外のものとの関わりを断っていた時期のことを綴ろうとしても、それは平穏な「私」として経験したものではなかったのに。
「引きこもり」の時には一日一日を過ごす神経がすり切れたみたいになっていて、知覚も記憶も明確に刻むことがなく、自分自身の考えや意識な んてあいまいなままで年月が過ぎていっていた。
眠りについている人が夢を見ている最中の自分自身を記述できないように、また、酩酊状態にある人が自分の言動を客観的に判断できないことのように、そこにいた「私」は私の体であっても「私」として語れるとは限らない。
闘病記が書かれるのは激痛に見舞われるような病苦のピークを過ぎたあとのことで、自分にどのようなことが起きていたのか分析まじりに書けるのは苦しみが過ぎ去ってからでなければならない。
苦しみの渦中にある最も書かれるべき「私」の心身は終わっていて、月日の過ぎた現在の「私」が過去の「私」を代筆することによって書くべきことが書かれる。
けれど自分との距離が大きすぎる時や、自分が自分ではなかったと感じられるよう な時、私は「私」として語れなくなってくる。
自分を見つめることの難しさ
最もその距離が遠かったのは十代の後半で、当時の「私」は人との交流のない「引きこもり」的な状態を極め、誰かと顔を合わせることが一切なかった。
混沌とした精神状態だったものの自らメンタルクリニックに接続し、精神科医と会話したのが一年ぶりくらいの他人との対面だったと思う。
受付で自分の名前を書く時には神経の過敏さによって外界と自分との境目がごわごわで、発言のために喉からひねり出した自分の声は重度の風邪引きのように粗(あら)い低音だった。
「私」は精神科医のしゃべっている単語の一つ一つは理解できても、頭の中で文脈が バラバラになってしまって会話を成立させられず、後に「統合失調症」の診断を受けることになる劣悪な精神状態でいた。
「引きこもり」の不社会的な関係も、教育上のマイノリティにされたことも、養育者との心理的な葛藤も、セクシャリティに関する苦痛も…多くのことが人生の課題としてかたまりあって混沌の「原因」をかたちづくっていた。
「私」にとっては外出一つが極端な緊迫感をもたらすことで、町中のすれ違う人や車の運転席からの人の視線を恐がり、歩くための腕や脚の基本的な動かし方を忘れるくらいの混乱をきたしてしまう。
かといって部屋の中にいても、骨の髄まで染み込んでくるような自分自身への否定意識が突き刺さり、神経を休ませることなく四六時中磨耗(まもう)させて しまっていた。
噛みあわない会話に精神科医が失笑したくらいに「私」の人格は粉々だったし、自分を冷静に見つめ考えられるような状態ではなかった。
三人称を一人称にするような語り方
当時の「私」が自分自身の状況を理解するためには、「彼」はこのようにしている、という二人称を一人称に翻訳するような手間をかける必要があった。
自分が当たりまえのものとして自分でいられるだなんていう「一般的」らしい感覚は、私にとって人間社会の能天気な迷信みたいに感じられてきた。
年月を経てこの文章を綴る今日の私が十代の「私」を欺瞞なしに書くというのは、二人称どころか三人称を一人称に改変して、さらにそれを黙っている確信犯の翻訳家みたいなもの ではないのか…。
私が「私」として語るためには、たとえば学者が研究対象の集団の中に自ら入り込んでおこなう観察と分析の手法のように、第三者でありつつ内側から見る視点が必要になってくる。
これから先に書かれる私についての文章はたぶん、自分研究でありながらも、根本的なところではたった一人の『引きこもり』のためのエスノグラフィーといったおもむきになるほかない。
患者はどんな医者よりも痛みを知っている
オーストリアの作家、インゲボルグ・バッハマンの詩に、『火傷した手で火の性質について書く』という一節がある。
その火傷した手指の持ち主は、科学的な炎熱についての知識はないか もしれないし、正確に記述するための技能もないかもしれない。
けれど、どんな患者であっても痛みは医者よりも知っている。
「私」が「引きこもり」について何か書くのであれば当事者としてであって、心理学者でもなければ支援者としてでもない。
書かれるのは、あの時代のあの場所で、あの経験とは何だったのかという、まったくの過去になっているわけでもない苦渋に追想する一人の「引きこもり」の痛みになる。
たった一人で孤独に過ごしていた人間の、最も近いところにいた一人きりしかいない証言者の位置に立って、そこから、私は書き始める。
(続く)
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ
皆様のご購入がひきこもり新聞への支援になります
1月号「女性のひきこもり」ご購入はこちらをクリック