
(文・ぼそっと池井多 / Photo:「Sudan Railway」Wikipedia)
やっと列車が出た
前回「ひきこもり放浪記 第9回」までお話してきたワディハルファから、
やっと列車が出ることになった。
この閑散とした砂漠の村のいったいどこに、
これだけの人が待っていたのだろう、
と思うほどたくさんの乗客が駅に集まってきた。
列車はたちまち満員となった。
「満杯」といった方がよいかもしれない。
6人がけのボックスには8人が詰め込まれ、身動きが取れない。
通路にも、網棚の上にも、車両の屋根にも人が乗っている。
今にも落ちそうな格好で、手すりからぶらさがっている男もいる。
出発してまもなく、夜になった。
時速は20キロぐらいだろうか。
日本の感覚からしたら、かなりゆっくりしたスピードで、
列車は漆黒の闇のなかを南へと下っていく。
右も左も砂漠である。
しばらくウトウトとしたが、苦しい体勢なので寝つけない。
時計がないのでわからないが、すでに夜半過ぎだと思われる。
座席の客はもちろん、網棚や屋根の上の乗客たちも、
皆したたかに、スヤスヤと眠っている。
車両の中には、汗のにおいが充満していた。
アラブ世界からブラック・アフリカへと南下するにつれて、
人々の肌が褐色から黒へと濃くなっていき、
彼らが発する体臭も、
パッション・フルーツのようなにおいへと変化している。
「自分は今、アフリカにいるのだ」
ということが、この時になって不思議と、あらためて感じられた。
幼いころから私がテレビの中に観ていたアフリカとは、
同じようで、どこか違う感じがした。
眠れない私には、かつて日本で持っていたアフリカのイメージが
あざやかに思い起こされてきた。
深夜の回想
私の原家族では、母の方針で、
テレビはNHKしか見せてくれなかった。
1970年代のNHKというと、今とは格段の違いがあり、
ひたすらお堅い、子どもにとってはつまらないテレビ局であった。
毎週火曜日、午後7時半から8時というプライムタイムには、
「NHK海外特派員報告」
という報道番組が放送されており、
これを見ながら夕食をとるのが、我が家の習慣であった。
この番組では、まだ日本ほど経済的に豊かでない途上国が、
次から次へと取り上げられていた。
とくに、頻繁にあらわれるのが、不幸の大陸としてのアフリカであった。
貧困。飢餓。疫病。内戦。流血。
無数の人々が家を焼かれ、
難民キャンプで雨に打たれていた。
子どもたちはみな、骨と皮ばかりに痩せこけて、
ボロ切れのような毛布にくるまっていた。
彼らの唇には蝿がたかり、傷口には蛆(うじ)がわいていたが、
彼らにはもはや、それらを振り払う力もなかった。
そういう映像を見ながら、小学生の私は夕飯を口に運んだ。
食卓の横から、母の解説が入った。
「ほら、見なさい。
アフリカの子どもたちには、
食べ物がないのよ。
学用品もないのよ。
あの子たちは勉強したくても、できないのよ。
そこへいくとお前はいったい何。
たっぷりご飯も食べさせてもらって。
ノートも鉛筆もたんまり買ってもらって。
こんなにブクブクと太って、
ほんとに恵まれているんだから。
お前なんか、そういうありがたみ、ぜんぜんわからないでしょう。
そういうこと、もっとよくわからなくちゃダメなのよ。
そして、そういう環境を与えてくれてるお母さまたちに、
もっと感謝しなさい!
そして、もっと勉強しなさい!」
母は、自分のことを「お母さま」と呼ぶように、
幼時から私をしつけていたのである。
とくに悪いことをしたわけでもないのに、
こうして「NHK海外特派員報告」が放送されるたびに
私は叱られ、
夕飯もそこそこに再び学習机に向かうことになった。
小学校3年生からは中学受験勉強が開始され、
午前2時まで私は机に向かっていなければならなかった。
しかし、長く机に向かっていれば、
それだけ勉強できるというものでもない。
母の監視の目が遠のくと、すぐに私は力を抜いた。
すると、頭の後ろに第三の目でもついているのか、
たちまち母が勘づき、とがった声を降らせる。
「ほら、何をボケボケしてんの!
アフリカの子は、勉強したくてもできないのよ。
さっき見たばっかりでしょう!」
たしかに、私の机の上には、
アフリカの子どもたちが一生持てないほどの
ノートや鉛筆や消しゴムが転がっていた。
食べ物、学用品、モノ、モノ、モノ。
「お前みたいに恵まれて」
憎々しげに母はいう。
そういう母は、戦後の貧しい時期を生き抜いた人ではないか、
と人は想像するであろう。
私も、そこに母が私へ向けた憎しみの答えを見つけ出そうとした時期がある。
だが、その仮説は満足な答えを、私に与えてはくれないのである。
太平洋戦争が終わった時、母は9歳だった計算になるが、
田舎に疎開した裕福なお嬢さまとして育ち、
焼け跡の闇市を飢えてさまよった体験なども彼女にはない。
したがって、
「自身が飢えた体験があるために、そのようなことをいう」
とは解釈できないのである。
だが、社会全体が、
「幸福とはモノの豊かさである」
とでもいうような、高度成長期の平面的な価値観で測られていた時代に
母が生きてきたことは確かだと思われた。
「お前みたいに恵まれて」
母から憎しみの言葉をぶつけられるたび、
私は自分が生きていること自体、
たいへんな罪であるような気がして萎縮(いしゅく)した。
そして、
「こんな悪い自分なんか、ほんとは生きていてはいけなんだ。
アフリカでは子どもたちが飢えているのに」
と考えた。
ところがその一方では、不思議なことに、
母が「恵まれている、恵まれている」というわりには、
私はまったく幸福ではなかったのである。
転校も多かったため、学校ではいじめに遭い、
学校から帰れば、母から何かにつけ責められていた。
いま思えば、学校内いじめと家庭内いじめにサンドイッチされていたのだ。
経済的に「中の下」を行っている家庭であったが、
モノに困るということはなかった。
しかし、何かが決定的に欠けていた。
その「何か」を言い表わす言葉を、私が持てなかった。
当時はまだ「生きづらさ」などという言葉もなかった。
ロシアの文豪トルストイは書いた。
「幸福のかたちはいつも同じだが、不幸のかたちは人それぞれ違う。」
そうだ。私は不幸だったのだ。
しかし私の不幸のかたちは、
自分の不幸を不幸として感じることを禁じられている、
という不幸ではなかったか。
私は、モノの氾濫を
幸福として感謝しなくてはならない立場に追いやられていた。
なぜならば、そういう状態を幸福と呼ぶのだ、と母が決めつけていたからである。
母が決めつけていた、ということは、
世間が決めつけていた、ということであり、
そんな決めつけを子どもながらに私が
自分の内に取りこんでいたということでもある。
だから、私は「ボクは不幸だ!」と叫ばなかった。
泣き言一つ、言わなかった。
そのかわり、数々の精神症状を出した。……
このため、子どものころから私の意識の底には、
一つの疑念が焦げついていた。
「アフリカの人たちは、
ほんとうにお母さまがいうように不幸なのか」
私は、どうしてもこの目で見極めたくなった。
そうしないことには、母が私の奥底に埋め込んだ罪悪感が、
永久に払拭されない気がした。
しかし、アフリカは厳しい場所だ。
そんな、飢餓や疫病や内戦にあふれた大陸へ行ったら、
自分が死んでしまうかもしれない。
だから、こわい。
ところが私は、もう日本社会では生きていけないから、
死のうと思ったのだ。(「ひきこもり放浪記 第4回」参照)
どうせ死んでしまうのなら、
死んでしまうようなアフリカへ行くのが、ちょうどよい。
それが、私がアフリカへ来たほんとうの理由ではなかったか。
……。
そして今、夜行列車でしたたかに眠る、
彼らアフリカの人々の寝顔をまじまじと見ている。
彼らは不幸か?
「見極めなくてはならぬ」と私は思った。
列車は、首都ハルツームへ向かって、おごそかに南下をつづけていた。
・・・「ひきこもり放浪記 第11回」へつづく
——————————
紙面版ご購入はこちらをクリック
ひきこもり新聞をサポートして下さる方を募集しております。詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ
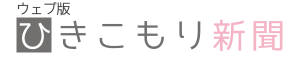


懐かしい番組名を見つけました。「NHK特派員報告」。わたしも見ていました。強制的にではなく、見ることが「優等生」であるのかのような意識で視聴していました、たぶん。その方面の教育に熱心な担任の指導もありました。いま、テレビ受像機がありませんので、NHKも見ることはありません。あの手の番組は少なくなってしまいましたね。
アフリカ行きの動機になったのが、あの番組であるというのに、興味をひかれました。「彼らは不幸か」「見極めなくてはならぬ」という筆者の思いこそ、まさに切実なものであり、強く共感を覚えます。続編に期待します。
ともひこさま コメントをどうもありがとうございます。
そうですか、『NHK特派員報告』、ごらんになっていましたか。
私も、もし高校生ぐらいで見ていたなら、もっとちがった観方をしていたかもしれませんが、なんせ小学校低学年のころでしたから、なにやら難しい番組という印象ばかり残りました。そして、何といっても、その番組をダシにして罪悪感をあおってくる母の言動がいやでした。
しかし、あの番組は心の深い所に残りました。そういうことが平明に思い返せるのは、いま私がこの年齢だからなのでしょう。
続篇も書かせていただくつもりです。